皆さん、ゲームは好きですか?
僕はめちゃくちゃ大好きで、今でもやっていますが小中高とほぼ毎日やっていました。(さすがにテスト期間は自粛してました。)
ゲームは好きだけど、あまりやらせてくれないという方もいると思います。
しかし、近年だとゲームは脳によい影響を与えるといわれています。
ではどのような影響を与えるのか、今回は書いていこうと思います。
結論
ゲームをすることの効果
ゲームをすることは時間の無駄といわれがちですが
カタルーニャ大学が行った116件の研究をまとめたメタ分析(今まで研究をまとめて結論を出すこと)で、ゲームをすることは
- 注意力を保つ力が増える
- ワーキングメモリーが向上する
- ストレスが高い状況下で集中力を保つ能力が高まりやすくなる
などのメリットを出しました。
ワーキングメモリーとは
短期記憶のことで、ワーキングメモリーが増えるほど短時間に多くの物を覚えておくことができるようになる場所のことを言います。
またストレスが高い状況下で集中力を高めることができるので、発表前や試験前でゲームをすることで集中力を維持できる期待もできます。
実際、嵐の二宮は本番前はよくゲームをしているそうですが、ある意味正しいのかもしれません笑
他の研究でもチームプレイが入るFPSでは協調性も高まるというのもあります。
他人に気づかう必要があり、なおかつチームで行動するので、一人で突っ走ることがなくなりそうですよね。
脳に良いゲームの種類は?
ではどのようなゲームが脳にいいのでしょうか。
この研究では
- リアルタイムの判断を要求される
- 謎解きの要素がある
- 3D空間を飛び回れる
という条件をそろえることで認知トレーニングとしての効果が高まるみたいです。
これらのことを踏まえると
- マリオの64
- ゼルダの伝説
- モンハン
などが挙げられます。
全てを満たしていなくてもいいと思いますが、認知トレーニングとして取り入れたいなら、これらがよいのではないのでしょうか。
ゲームのデメリット
もちろんゲームをすることでのデメリットも存在します。
何が悪いのか見ていきましょう。
依存性
まあこれはゲームをやったことがある人はわかると思います。
これは厄介なもので、ゲームをやりすぎることで、せっかく集中力を高め頭をよくしたのに、勉強しなければ本末転倒です。
ではなぜゲームには依存させる力があるのでしょうか
それは報酬の予感を与えるからです。
ゲームをしている最中、主人公は成長しますよね。
成長することで何か新しい能力や技が手に入るかもしれないですよね。
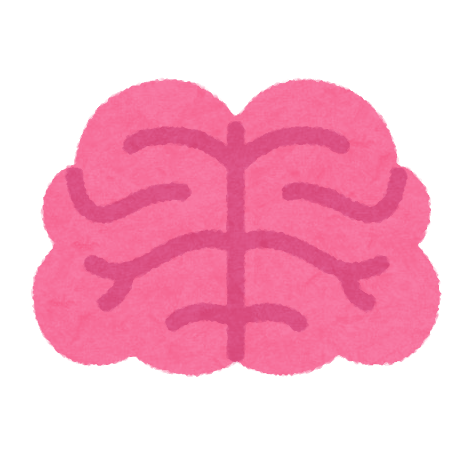
このモンスターを倒せば報酬がもらえるかも
というのが脳に刺激を与えています。
パチンコをやる人は、お金を入れることで当たりがでるかもと考えます。実際に当たった場合は快感得て、また課金をしてしまいます。しかし当たらなかった場合は、次こそは当たるかもと期待し、依存してしまいます。
これもゲームでよく使われている方法です。
これがすべての要因ではないですが、依存的にさせる要因の一つになります。
報酬になれてしまう
ゲームをすると報酬が来ることが当たり前になります。
そしてその報酬は目に見えるもので、ギリギリの難易度で設定されています。
そこから快感を得ることで、リアルの勉強などには興味がなくなってしまいます。
簡単に言うと

勉強はやっても何も報酬が出ないし、能力が上がったのが目に見えないからやる気にならない。
みたいな感じです。
こうなってしまうと、リアルの成果も追い求めようとしないでゲームに依存してしまう可能性が出てきます。
長時間やる対策方法

ゲームをすることは一長一短です。
依存してしまえば危険な状況になるが、うまく使えれば、頭をよくできるという強みもあります。
ゲームはほどほどに止めておきましょう。
まとめ
今回はゲームのメリットデメリットについて解説しました。
ゲームには頭をよくするという効果があるのは知らなかった人が多いと思います。
これで心置きなくゲームができますね笑
しかし、しっかりと時間を決めたうえでやることが大切です。
ゲームとリアルを充実させながら生活しましょう!
ここまでありがとうございました。


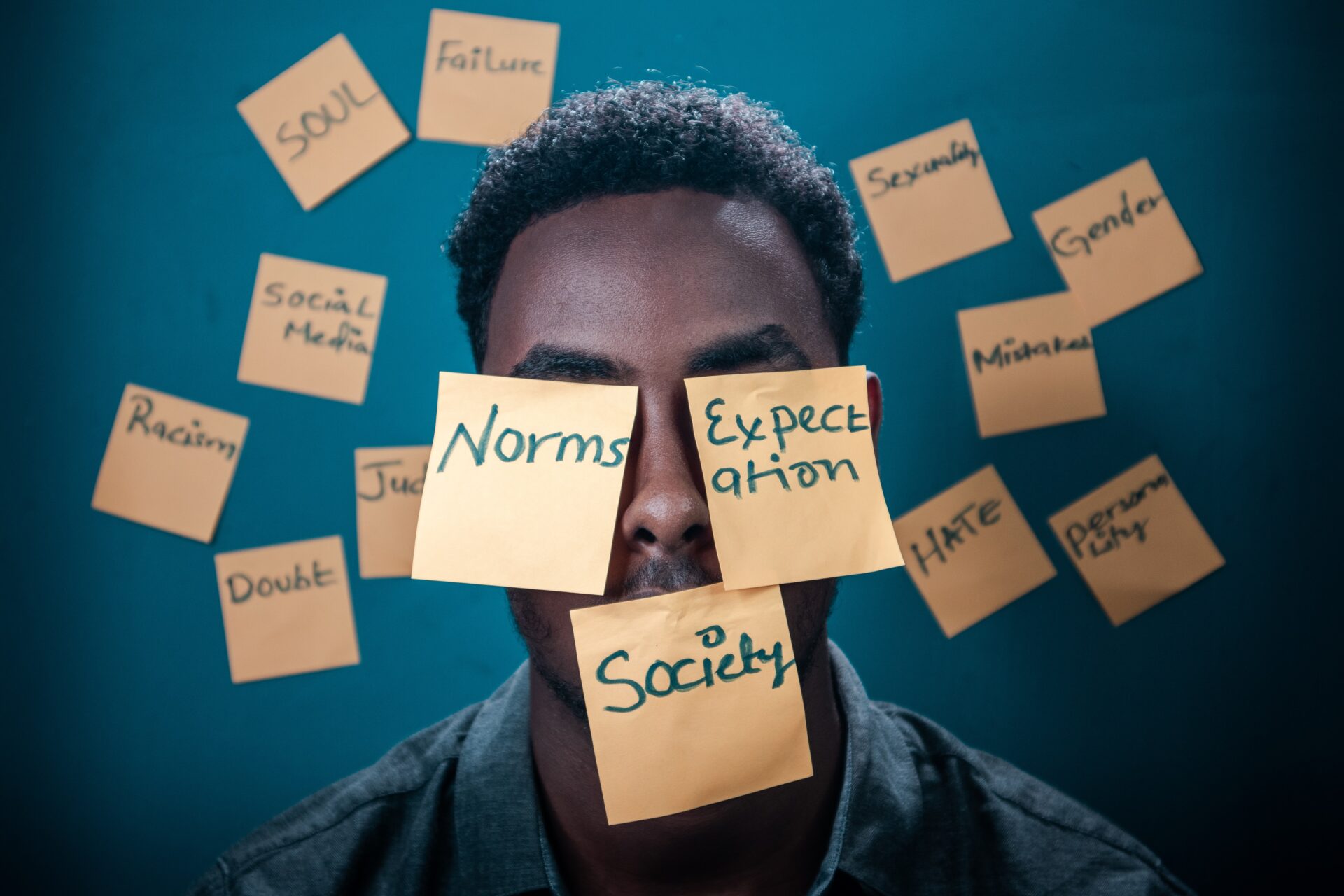

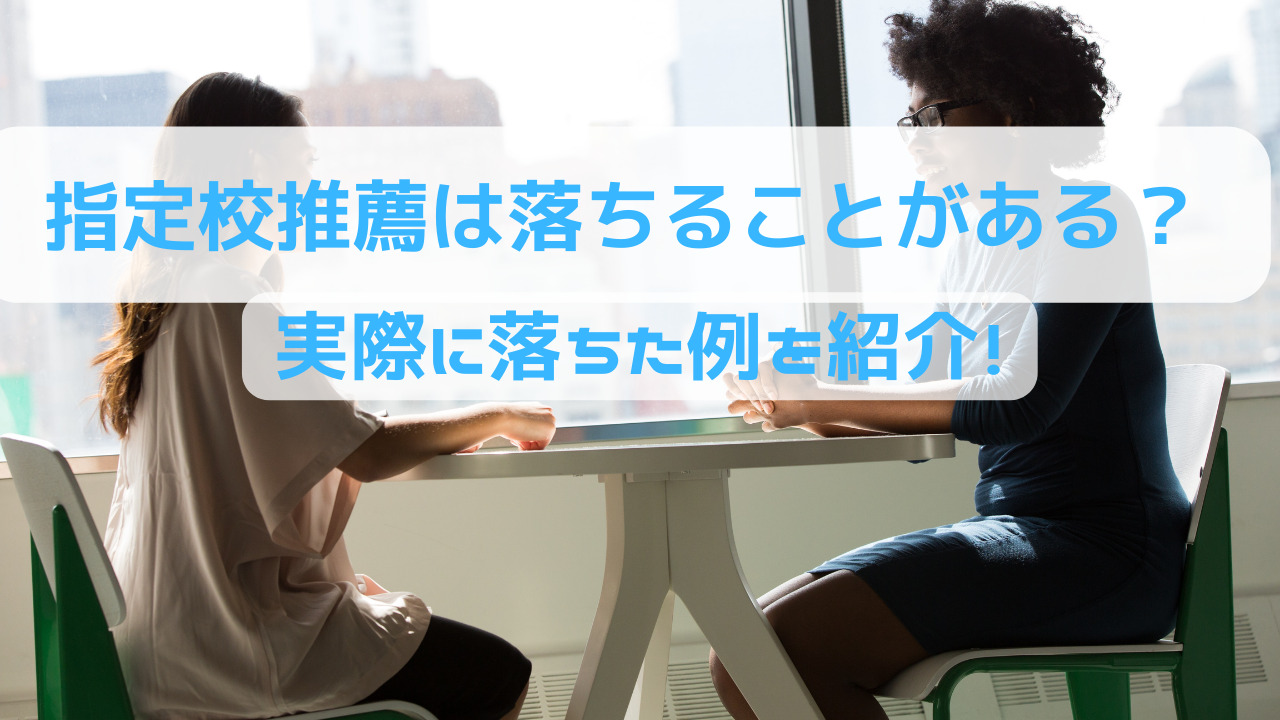
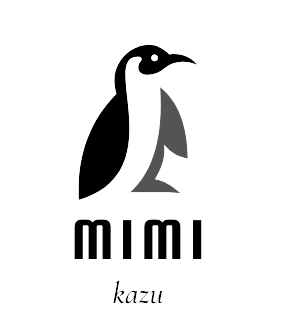



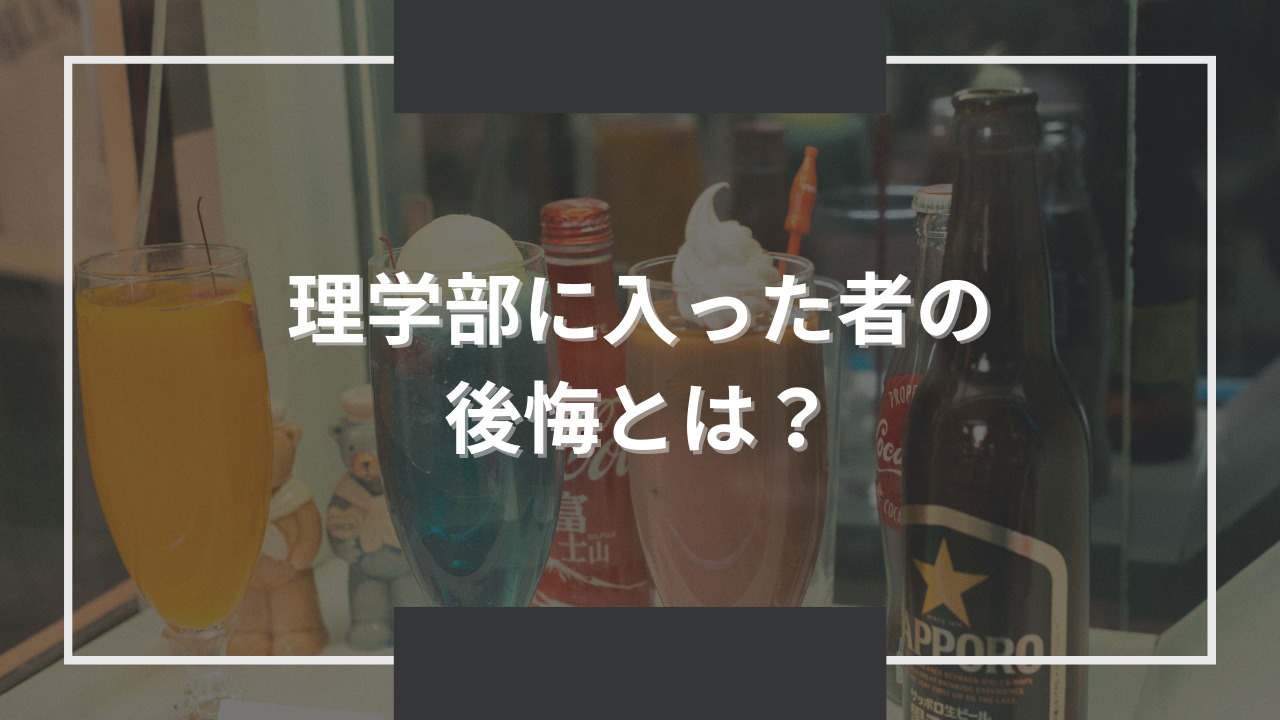
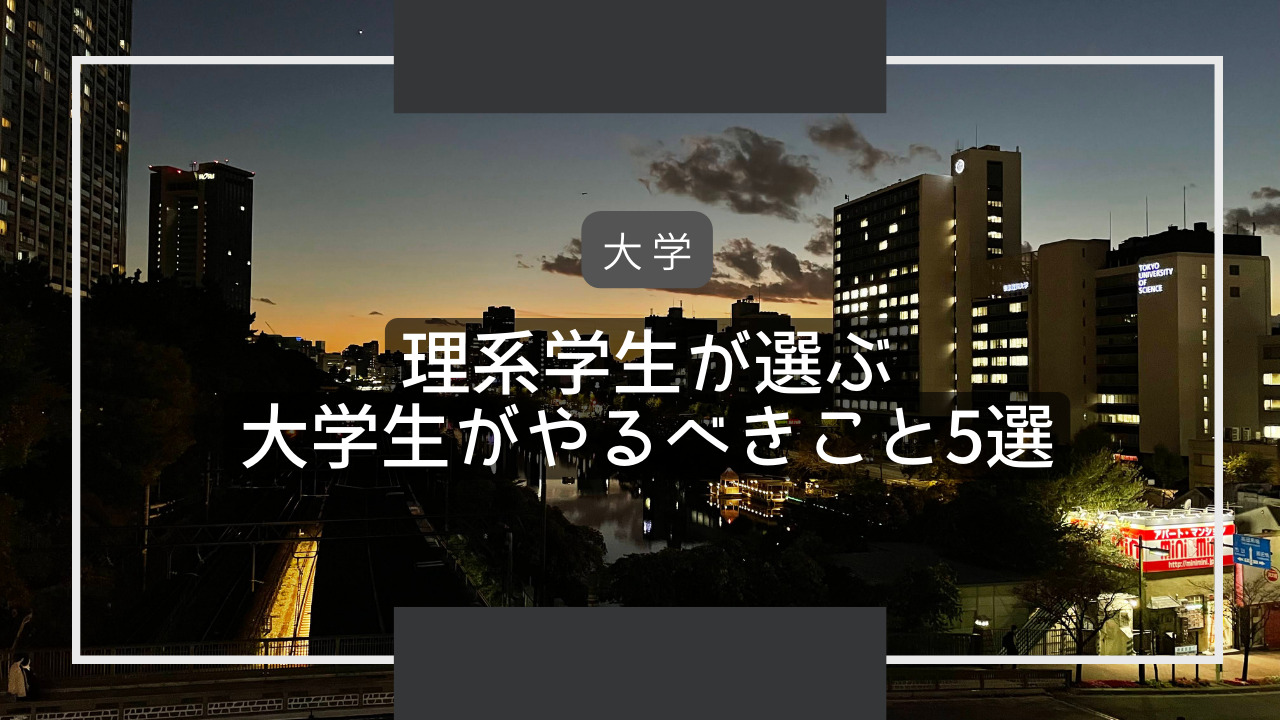

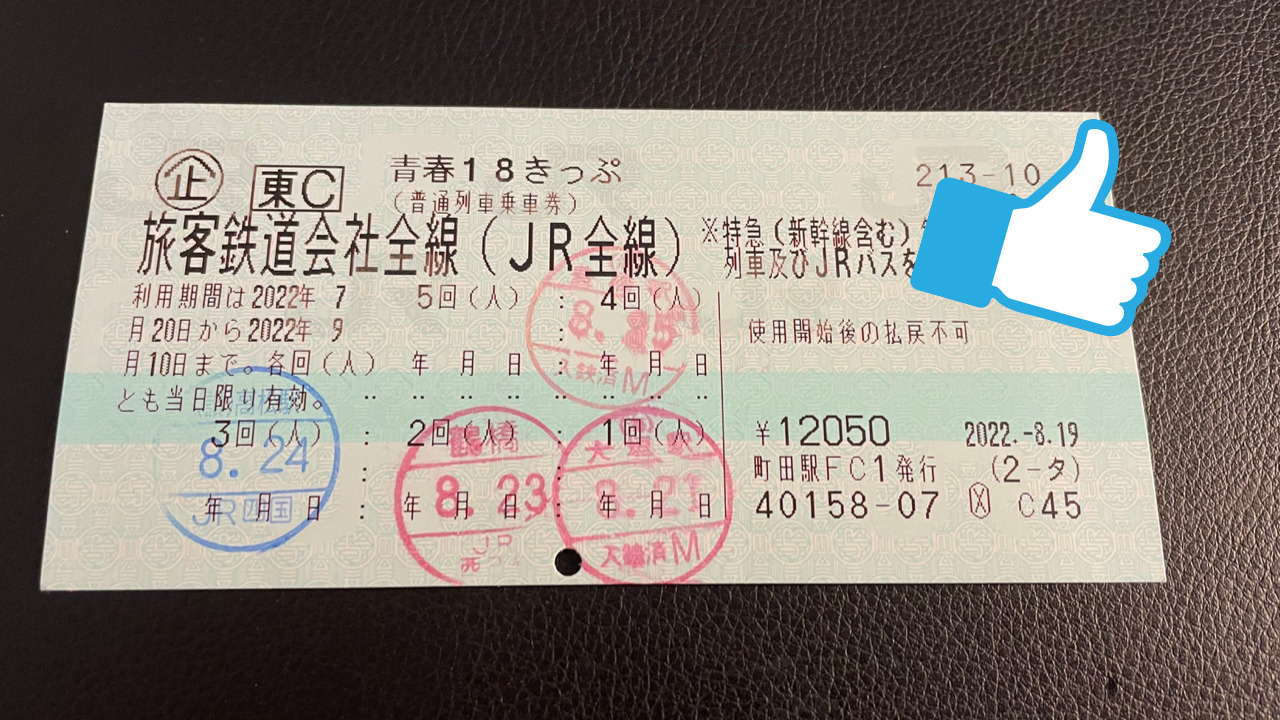








コメント