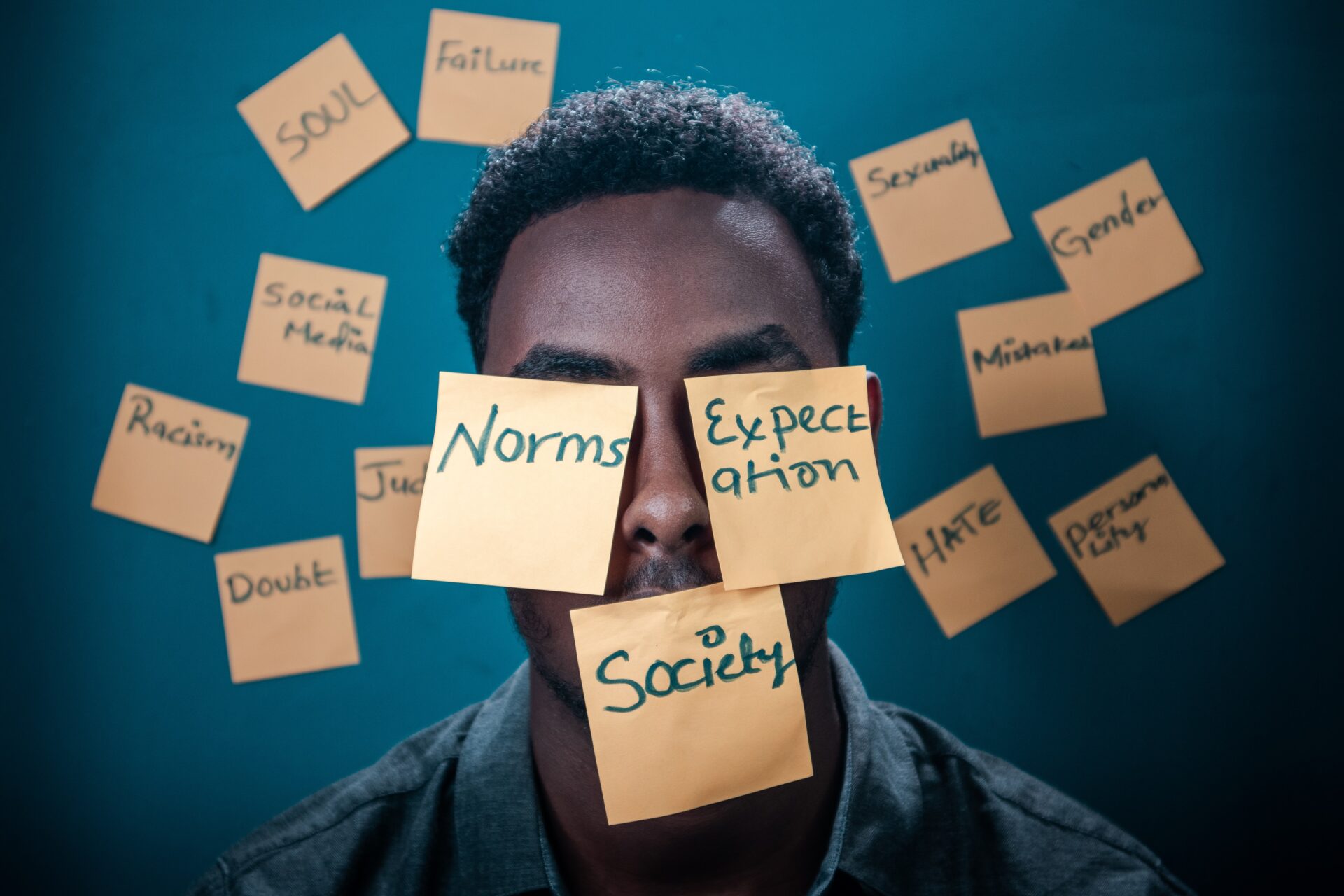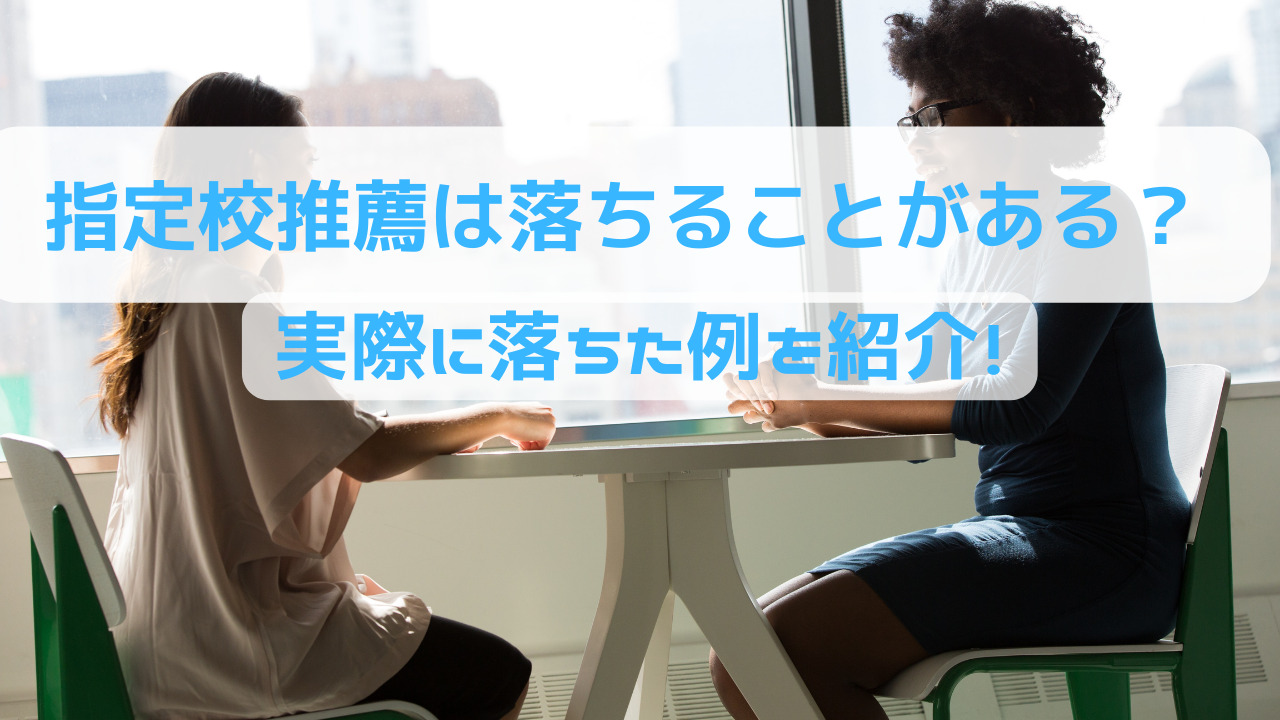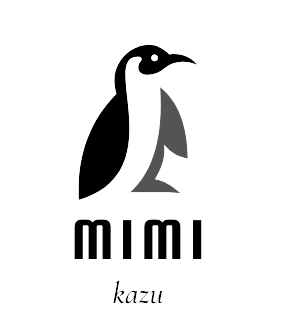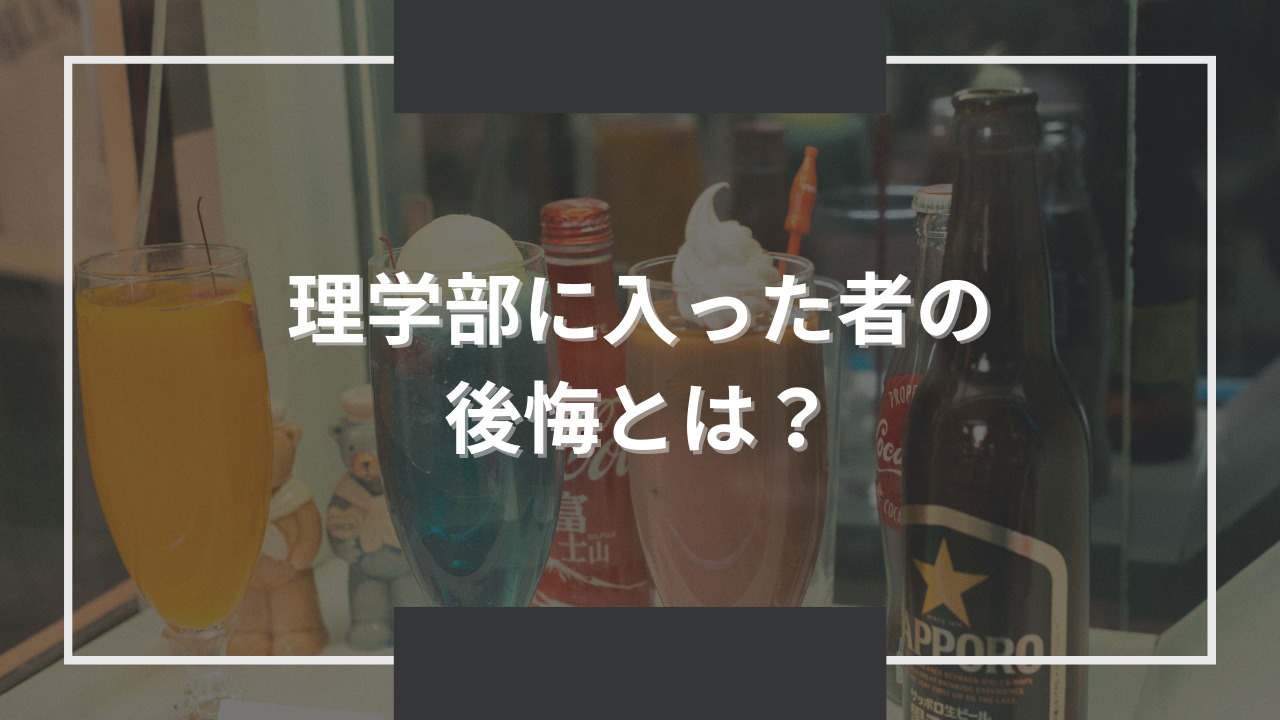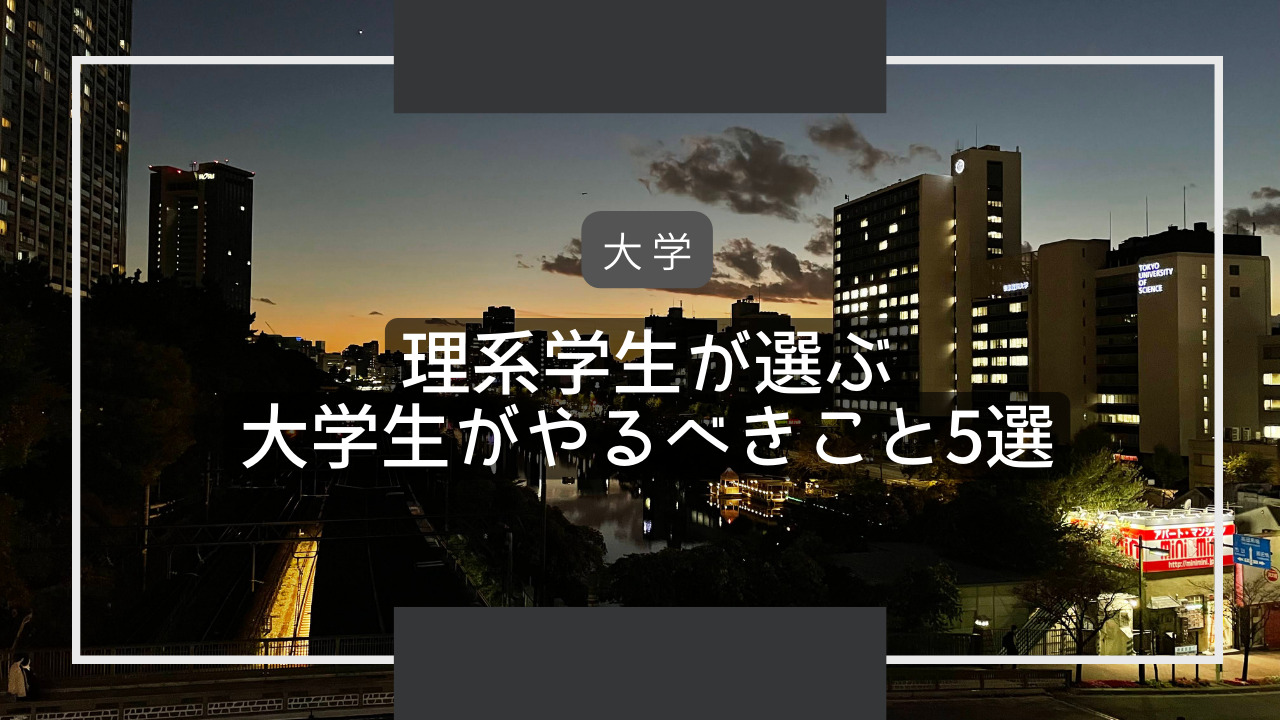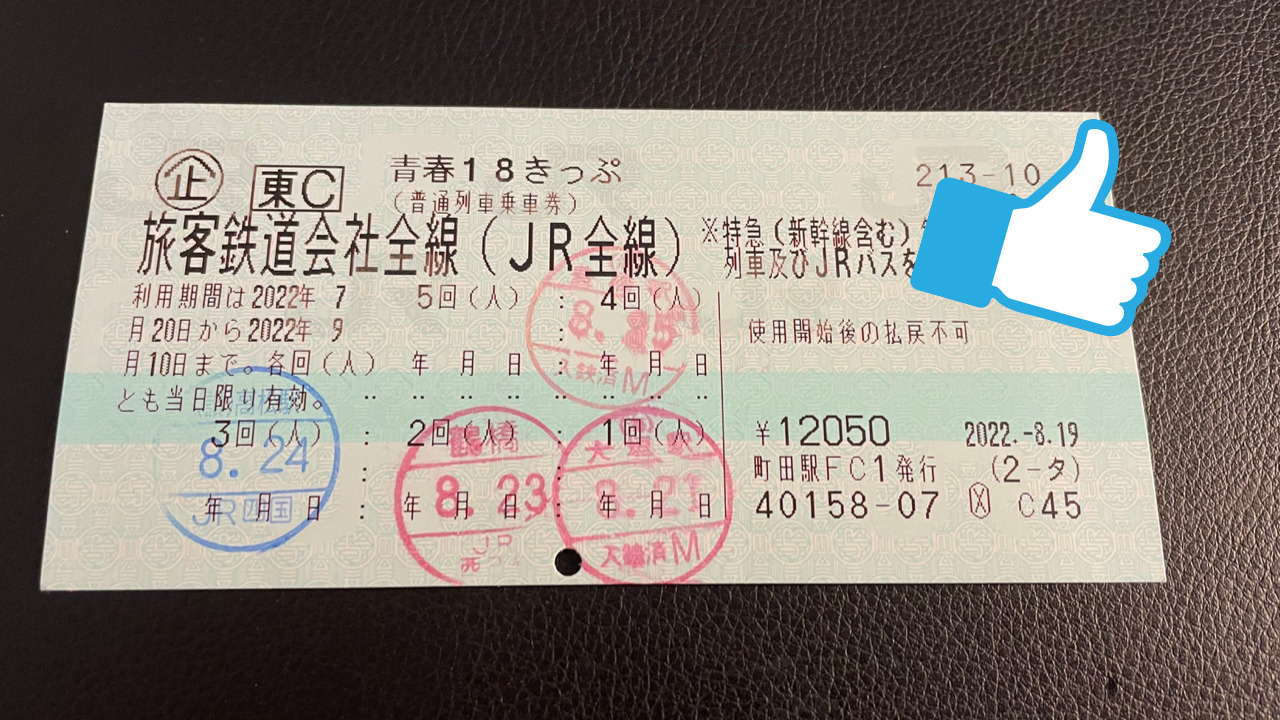勉強をやっていてもふと疲れてしまって、何もやる気が出なくなってしまったときとかありませんか。
何のためにやっているのだろうと思ってしまうこともないですか?
そんな時は自分にご褒美をあげてやる気をあげましょう!
ただし、これにはある工夫が必要になります。
今回はその工夫の仕方と応用の仕方について考えていこうと思もいます。
結論
ご褒美とはピーナッツ1、水1杯、チョコ1粒など
外発的動機づけと内発的動機づけ
教育論には
子供が何かを達成した時にご褒美を与えるか与えないか
の議論があります。
何かご褒美を与えて、やる気を出せるやり方を外発的動機づけといいます。
もちろん、子供としては何かご褒美がもらえた方が嬉しいですよね。
しかし
ご褒美につられてばかりではご褒美がなければやらないという事態になりかねません。
たまに勉強が好きで、たくさんやるという人がいます。
そのように自分の好奇心から積極的に勉強することを内発的動機づけといいます。
もちろん内発的動機づけのほうが成績もいいのですが

勉強なんか好きになれるか!!!
という人もいると思います。
そんな人は自分自身にご褒美をあげましょう。
そしてそれを小さな報酬にすることがカギとなります。
小さなご褒美にするメリット

でもさっきご褒美は自主性をなくすからよく無いって言っていたじゃん
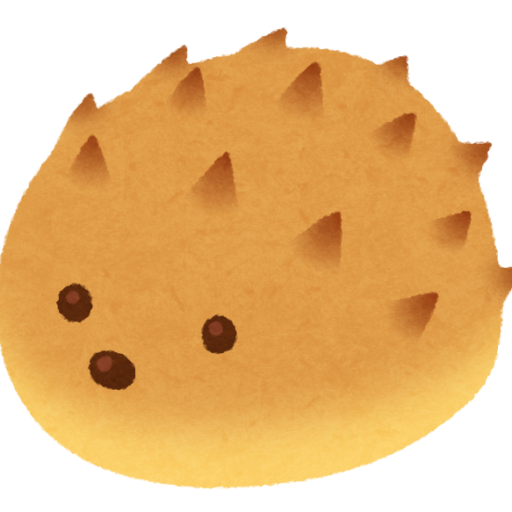
小さなご褒美にすることで「外発的動機づけ→内発的動機づけ」に無理やり持っていくのだよ
宿題を提出することで成績をつける実験をしました。成績に何も影響がない微々たる点数を与えたグループと何も点数がつかないグループに分けました。
なぜこのようなことが起きたのでしょうか
認知的不協和

成績に影響がない微々たる点数をもらうことで、人はこれを何のためにやっているのかと考え始めます。

俺はこんなちっぽけな報酬のために何をやっているのだ
みたいな感じです。
そして何のためにやっているのか意義を探そうとします。
意味が分からないという人は例を見ていきましょう。
タバコは身体に悪いと思っていながらも、吸うのがやめられません。
「タバコは害がある」という知識と実際にやっている行動に対する矛盾を感じ
不快になることを認知的不協和といいます。
その矛盾を解消するために無理やり別の思い込みをはさみます。
さっきの

俺はこんなちっぽけなご褒美のために何をやっているのだ
ということを考え、
ご褒美が小さすぎるとご褒美が小さいのに勉強をしているという矛盾の中から
勉強の中から無理やりやっている意義を探そうとします。
このような脳の思い込みが、やる気へと結び付けているのです。
小さなご褒美は何がいいの
僕のおすすめとしては
- チョコ1つ
- ピーナッツ1かけら
- 水1杯
そのようなものがいいと思っています。
とりあえず満足できないぐらいのご褒美を25分後に挟むというのがいいです。
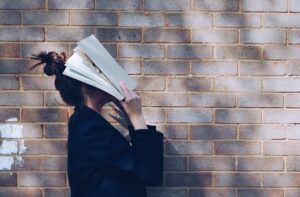
まとめ
今回はにわかに信じがたいことを紹介しました。
しかし、実際やってみると分かりますが本当にじわじわとやる気が出ます。(僕は水1杯でやりました。)
これは自分でやってみて、体感してみるのがいいです。
何回か実験して特に何も感じなかったらやめればいいと思います。
このようにして自分に合う形で勉強を進めてみましょう!
ここまでありがとうございました!
頑張っていきましょう!