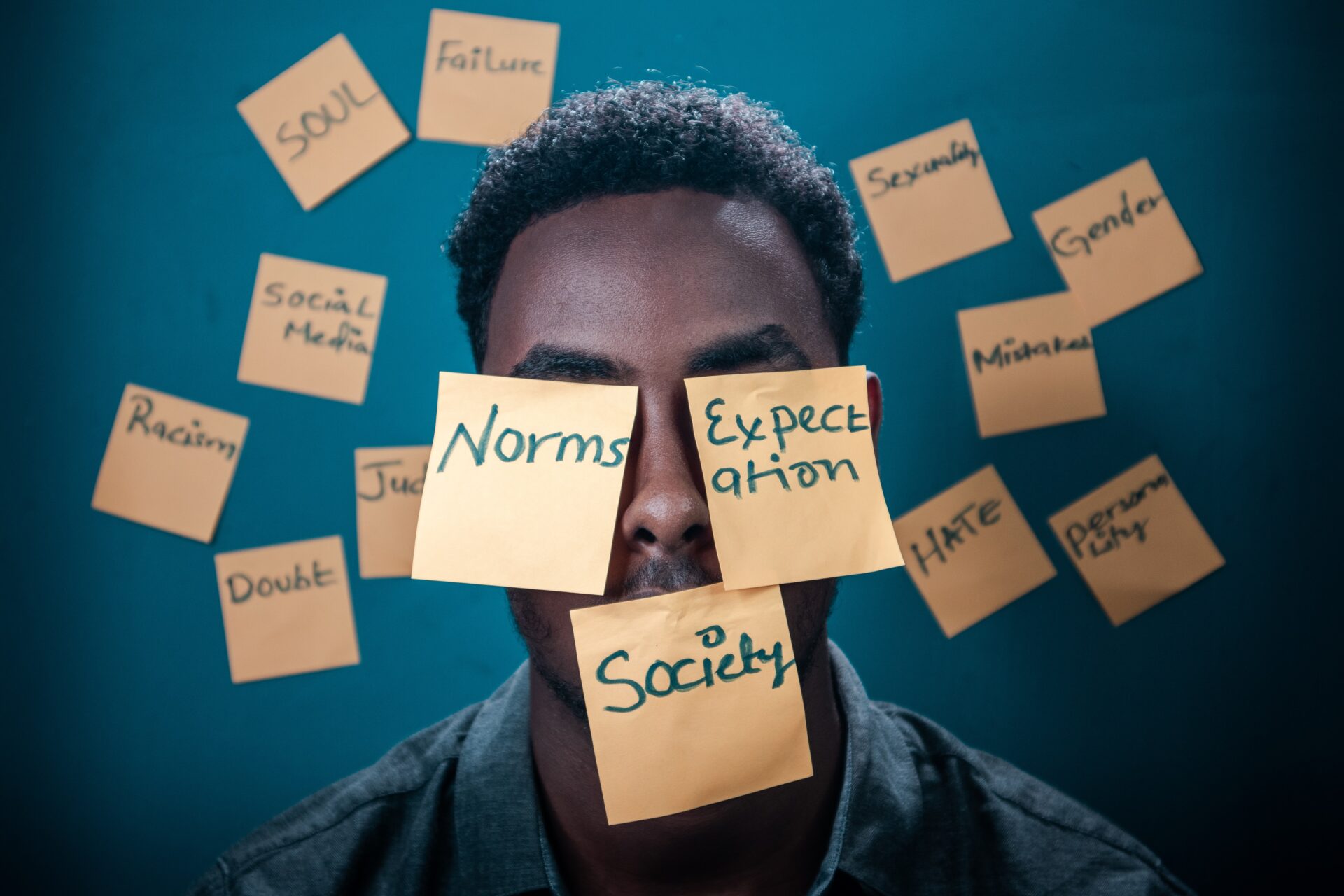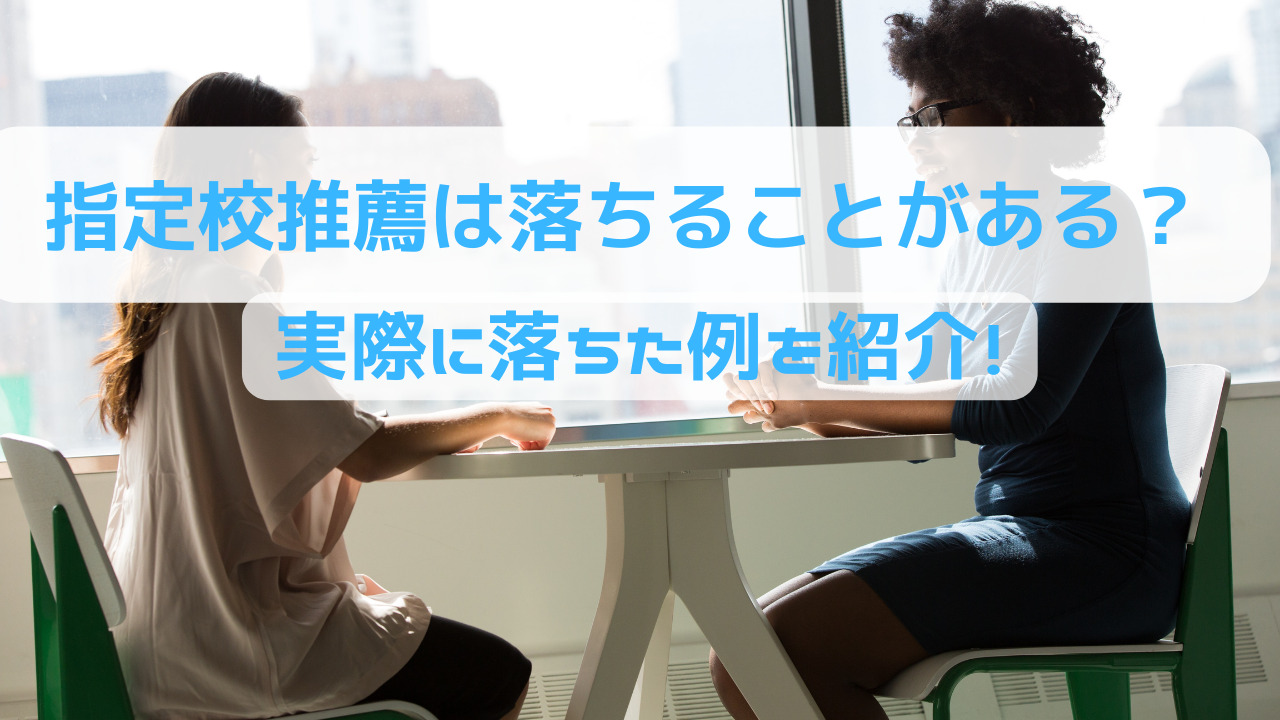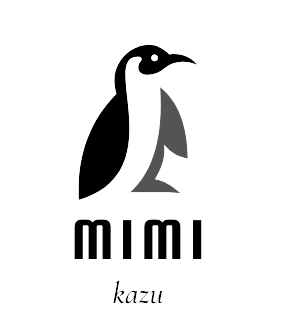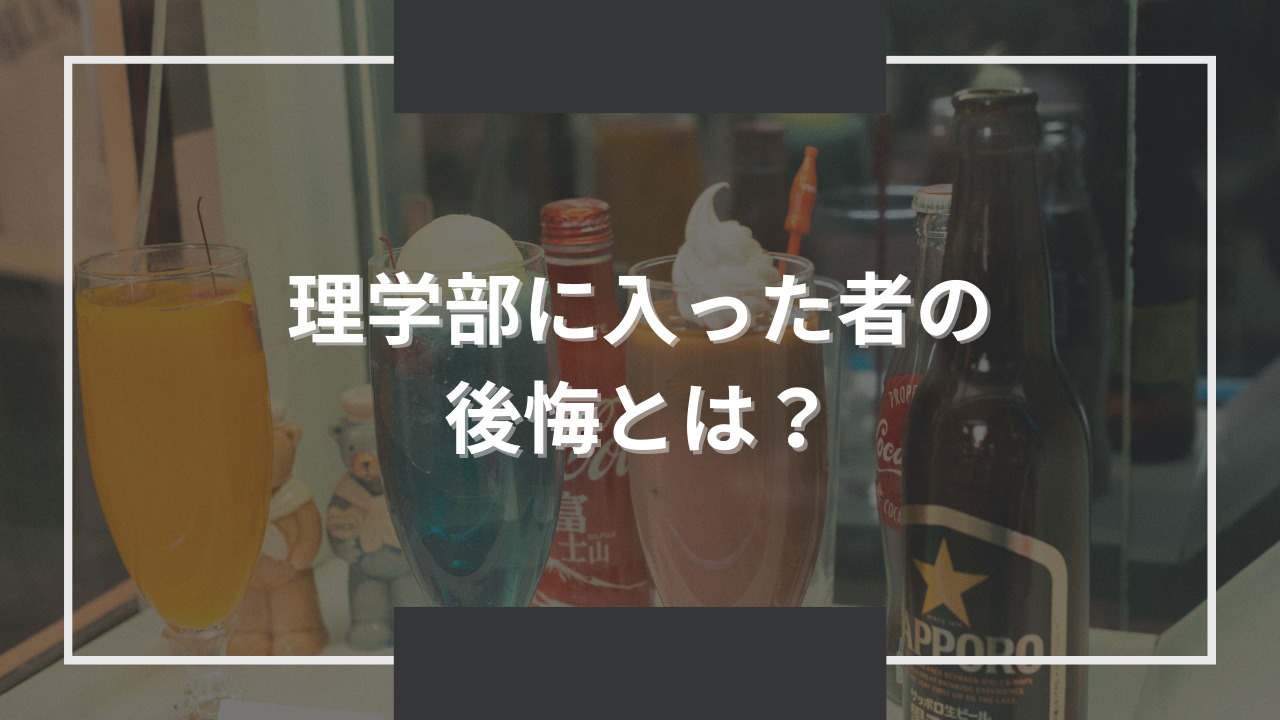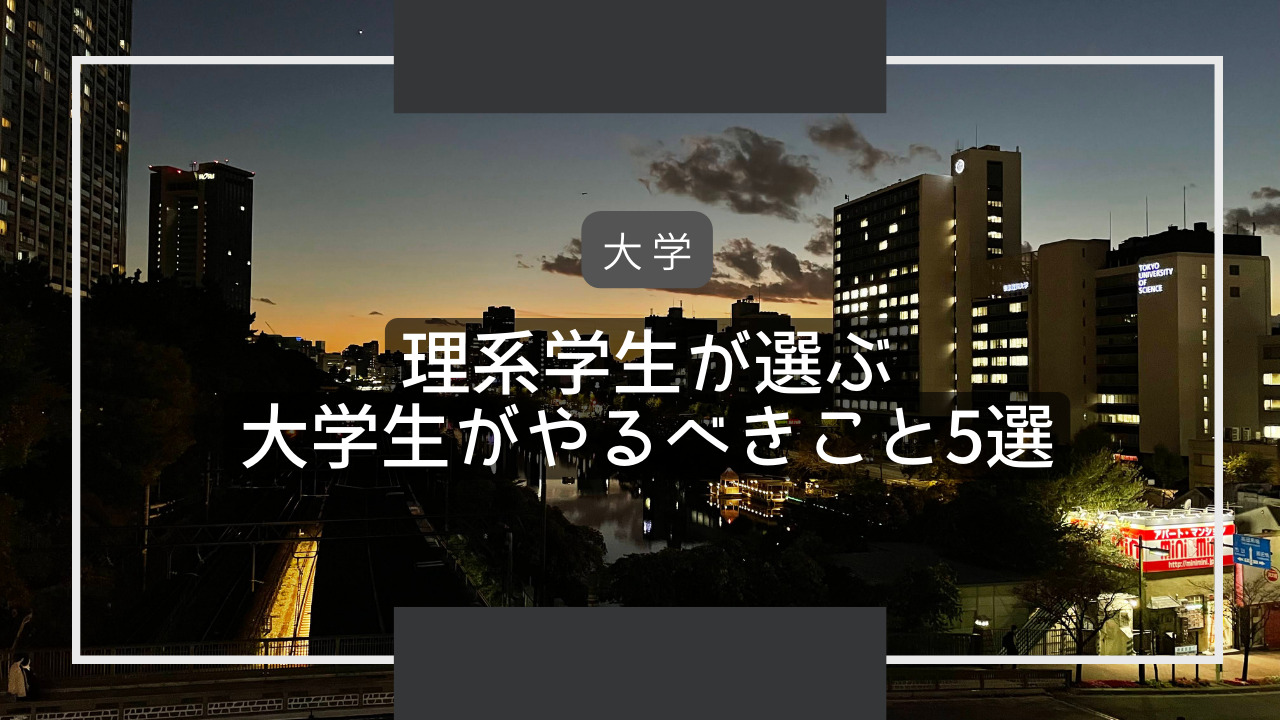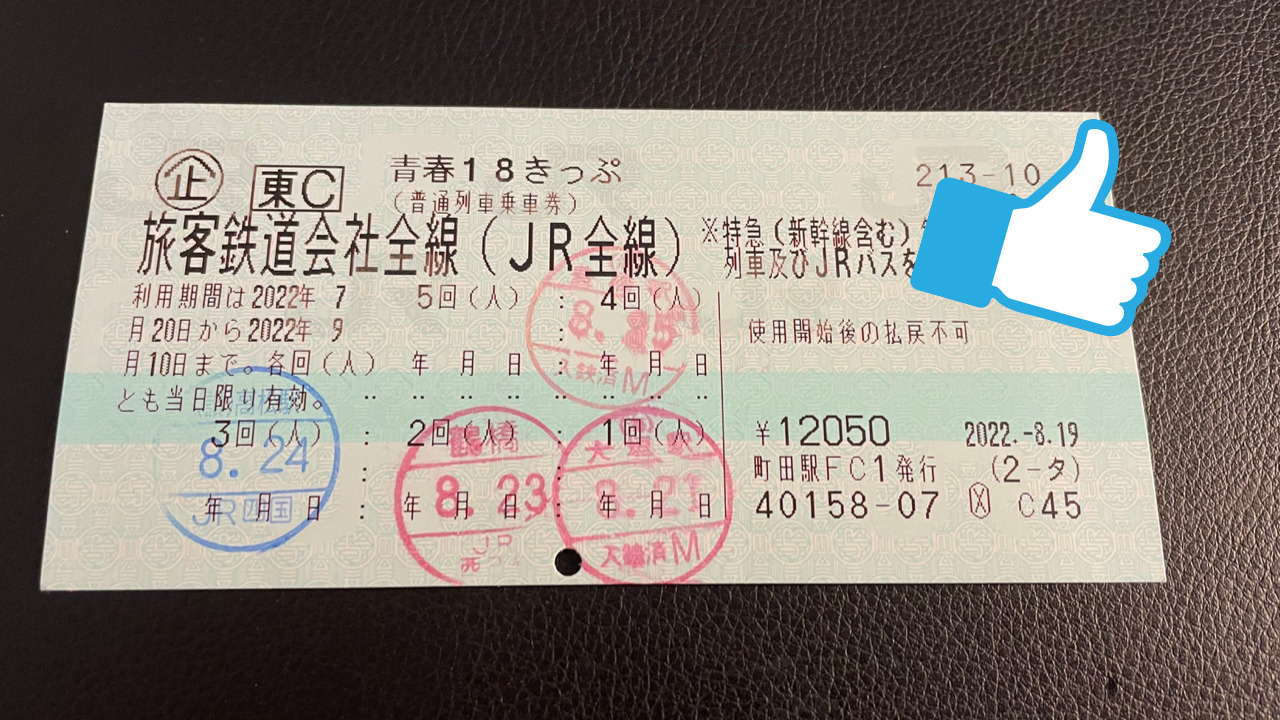このように考える人は多いと思います。
実際に僕も夏休みに目標としていた”勉強時間”はありました。
では受験生は夏休みや休みの期間中はどれだけ勉強すればいいのか書いていこうと思います。
結論
- “勉強時間”は個人の学習能力・志望校によって変わってくる。
- 自分の現在地と目標とする志望校を把握し、計画を立てる必要がある。
そもそも人はどれだけ勉強できるか違う

テスト勉強どれだけやったー?
このようなテスト期間でよくある会話だと思います。
全然やってないといっていながら点数が高い人って結構いますよね。
しかし、彼らは裏切っているわけではありません。
その人が
- 頭がいいから短時間でも勉強が終わる
- 得意な教科であまりやらなくても大丈夫
裏でめちゃくちゃ勉強している
このような可能性があります。
当たり前ですが頭がいい人ほど効率よく学べるようになります。
なので
というものは意味がありません。
もし最低でもこれだけの時間をやろうといっている人がいても、
- そのようなことを書いている人が頭がいいからそれだけで十分だった
- あなたの頭があまりよく無いからそれだけの時間やっても足りない
このような可能性が出てきてしまいます。
つまり、
自分の学習能力・目標について把握しよう

そんなこと言われても、自分の能力なんてわからないから助けて!
このような人がいると思います。
このような人はまず過去問を解きましょう。
共通テストでも目指す大学の過去問でもいいです。
夏の時期は共通テストの方がいいかもしれません。
そこから自分が目指すべき得点はどのぐらいなのかを把握することができます。
自分が行きたい大学までにあとどれぐらい点数を上げる必要があるのか見ていくことで、どれだけ勉強すればいいか見えてきます。

もし行きたいところが無かったら?
その場合は大学に入ってやりたいことや、行きたい大学を早めに見つけるようにしよう。
やりたいことや行きたい大学を見つけることでゴールが明確になるし、計画も立てやすくなります。

とりあえず偏差値が高い大学でも大丈夫かな?
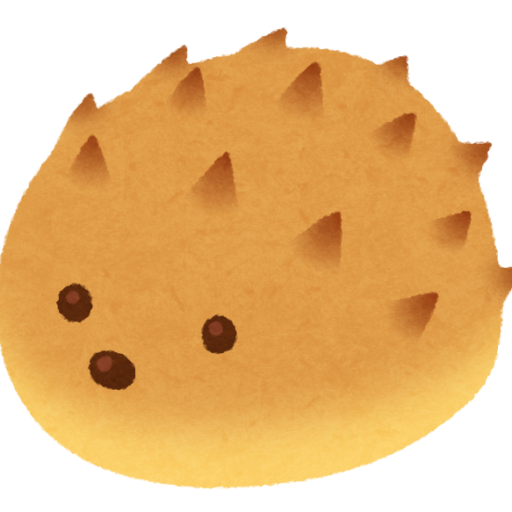
それでもいいよ。だけど偏差値が高い大学に行って、自分がどんな風になりたいのか、何を目指したいのかその先のことも考えようね!
目標までの計画を立てる
自分の目指すべきところ、今の自分の学力が分かったら
そこに行くまでの計画を逆算していきましょう。
逆算しながら受験までの期間にいくつかの中間ゴールを設定しましょう。
目標から現在に向かって計画を立てることです。
北京大学が行った実験では、このように逆算して行うことで、モチベーションがあがり目標達成率も高まったというのがあります。
またそのように逆算して計画を立てたグループは
- 10%~25%ほどパフォーマンスが向上
- プレッシャーに強くなる
- 勉強の先延ばしが軽減
さたそうです。
計画の立て方の例
例えば入試が3月なので
- 冬休み終わるまでに模試の判定をBにする
- 11月までに志望校の判定をCにする
- 夏休み終わるまでに共通テストを全教科8割にする
もし自分で立てた計画が難しかったり簡単だと思ったら目標の変更もどんどんしていきましょう。
受験までは長くてモチベーションが続かないこともあると思います。
なので、中間目標を設定することはモチベーションの維持につながります。
どこの分野から手を付けるべきか

目標はわかったけど、今日はどんな教科をやるべきなの?
これも最初にやった模試が役に立ちます。
その分野の基礎を固め、勉強することが大切です。
苦手なところをやるのは嫌だと思いますが、それをなくせば一番得点が上がる場所です。
苦手なところをなくすことは一番の得点upの近道なのです!
そしてまた苦手をなくした後、どこに手をつければいいかわからなくなったら、模試をやり、さらぶできなかったところをつぶしましょう。
模試や過去問を解くことはテスト対策で一番いいといわれています。
模試は定期的にやっておくようにしましょう!
まとめ
今回は夏休みというか、受験期の計画の立て方について書きました。
長期的な目標を立てることはあまりやったことがないと思いますが、これはかなり重要です。
なので立てた中間目標はカレンダーなどに書いておきましょう。
とりあえず、自分の現在地と目標を常に意識しながら勉強を頑張りましょう!
ありがとうございました!
長期休みの罠について解説しているこちらも見てみてください!