皆さんはテスト勉強をするときに教科書をどのように使いますか?
特に使わないよという人もいると思いますが、教師は教科書を参考に多くの問題を作ります。
なので教科書を読み込めば、テストでの高得点も夢ではありません。
ですが教科書の内容を読み込むのは簡単なことではありませんよね。
難しい内容が書いてあったら、読むのにも嫌になります。
なので今回は教科書や本の内容をしっかり読む込む方法を書いていこうと思います。
結論
- 一章を読んだら、重要なところを思い出しながらメモを取る
- 重要な部分を声に出して読む
覚える際には想起をする作業が必要
本や教科書をただ読むことは受け身の作業となり、知識として定着しにくいです。
ではどのように読む必要があるのかというと、思い出す作業を必ず入れる必要があります。
思い出す作業をすることで脳が印象付けるので、記憶に強く残ります。
先週のテレビで言っていた問題を友達が問題として出してきたとき、あと少しでひらめきそうなのに出てこない。
そして答えを聞いたときに、「あーそうだ、忘れてたわ」と悔しがり、もう忘れないようにしようと決めるなんてことあると思います。
こんな感じで思い出すことで、脳は何回も思い出すから重要なことなんだと判断し、記憶に残りやすくなるという原理になっています。
教科書を読む際には、読んだ後に読んだところの内容を思い出す
想起の方法を活用するためには、何回も思い出すという作業が必要になります。
一回やってみると分かりますが、結構忘れています。
もし忘れていたら、もう一度内容を見返して、また閉じて思い出してみましょう。
難しい内容なら一ページずつやってみてもいいです。
こうすることで、だいたい何が書いてあったか覚えることがことができます。
声に出して読んでみる

教科書の重要なところを声に出して読んでみましょう。
本でも重要だと思ったところを声に出して読むことで、記憶に残りやすくなります。
人は運動感覚を多く使って表現することで、記憶に定着しやすくなる
本や教科書を読むだけだと、目しか使えていません。しかし、声に出すことで聴覚も働かせるようになり、よりアクティブなトレーニングとなります。
他にも音読には自己参照効果があります。
自己参照効果とは
物事をすべて自分の事の様に変えて記憶に残すことです。
ちなみに僕は歴史が嫌いです。もう絶対やりたくないと思っています。特に世界史になると、赤点寸前になります。
なぜかというと、自分とは関連性が一切ないと感じるからです。遠い昔にあったことなんて覚えても仕方ないやろと感じてしまいます。
みなさんもこのように自分とは関係ないから覚えられないということはたくさんあるのではないのでしょうか。
しかし自分の周りの出来事や関係があることなら覚えられますよね。
「明日テストがあります」
これが友達のことならいちいち覚えませんけど、自分のことだったら覚えますよね?
これが自己参照効果です。
すべて自分の周りで起きたことだとイメージすることで覚えがよくなり、理解も促進されます。
歴史の場合は自分が実際に戦場に立っているイメージを描いて、実際の戦場でなにが起こったか自分もその現場にいることを考えることで自分事となり、覚えやすくるということです。
まとめ
今回は思い出しながら勉強をすることと、教科書を音読することをやりました。
これは小学1年生ぐらいからやってますが、結構重要ですよ。
ちなみに音読で起こる効果を心理学の世界では「プロダクション効果」といわれています。
名前がついているほどしっかり効果が実証されているので、皆さんもぜひやってみてください。
ここまでありがとうございました。



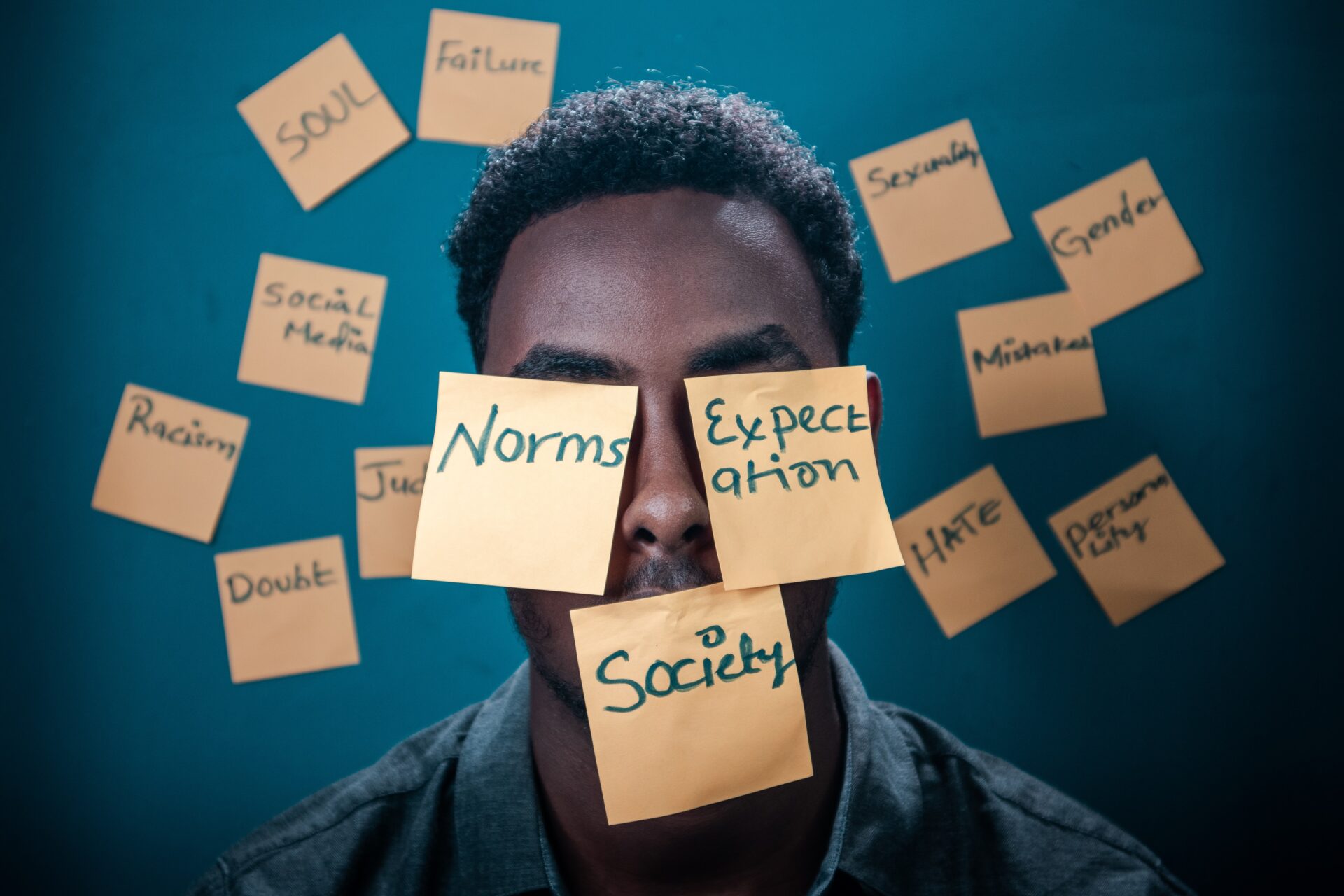

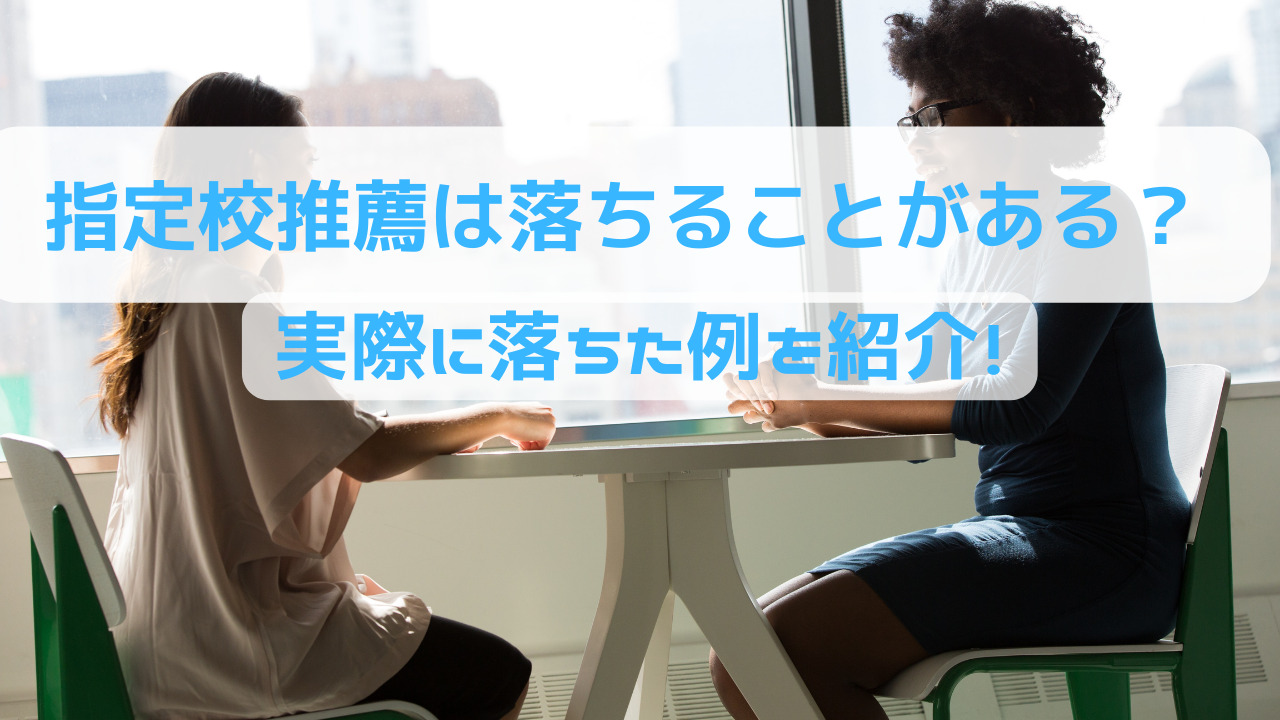
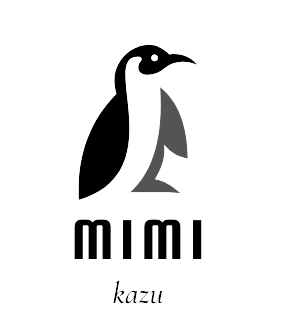
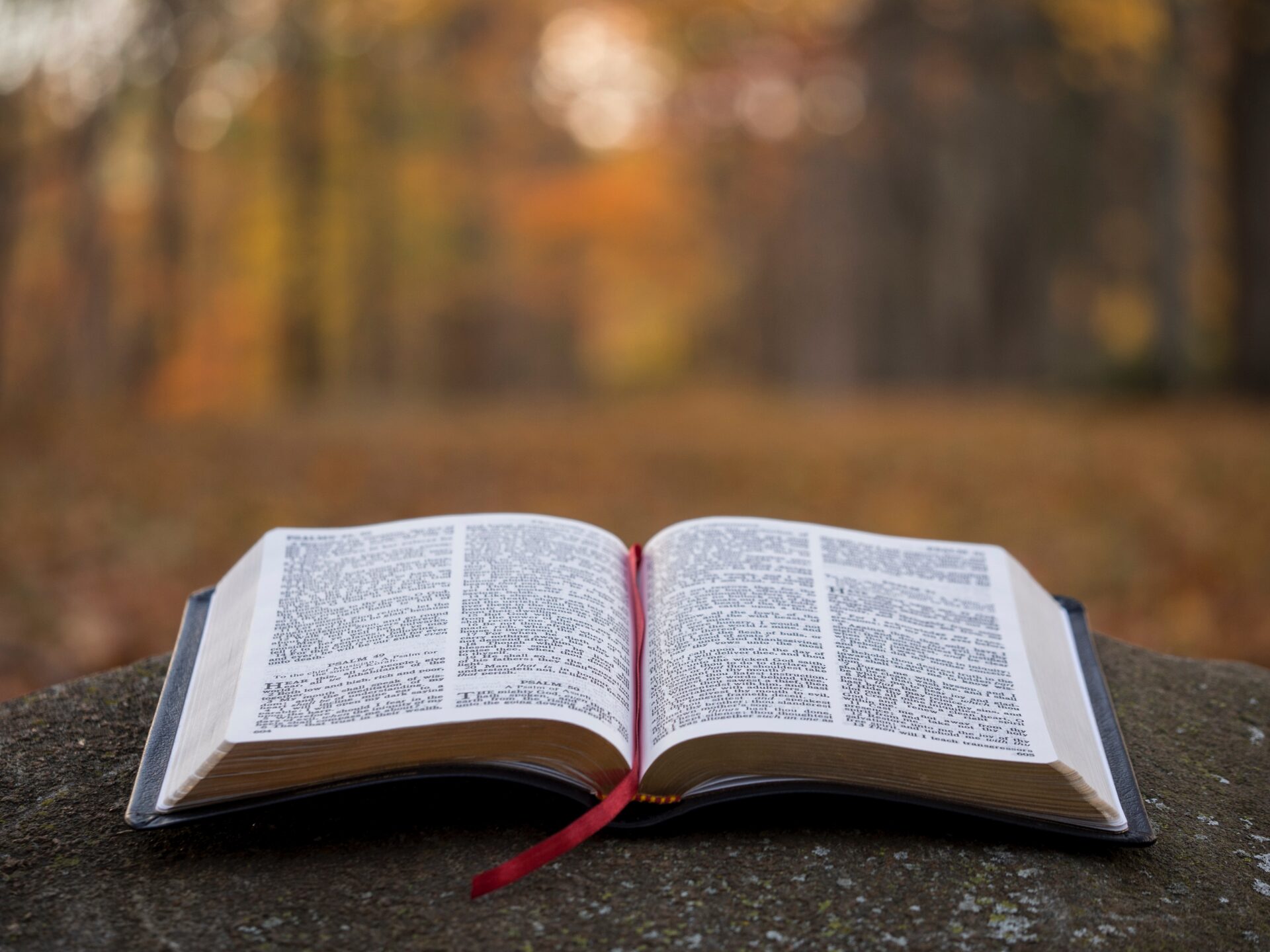


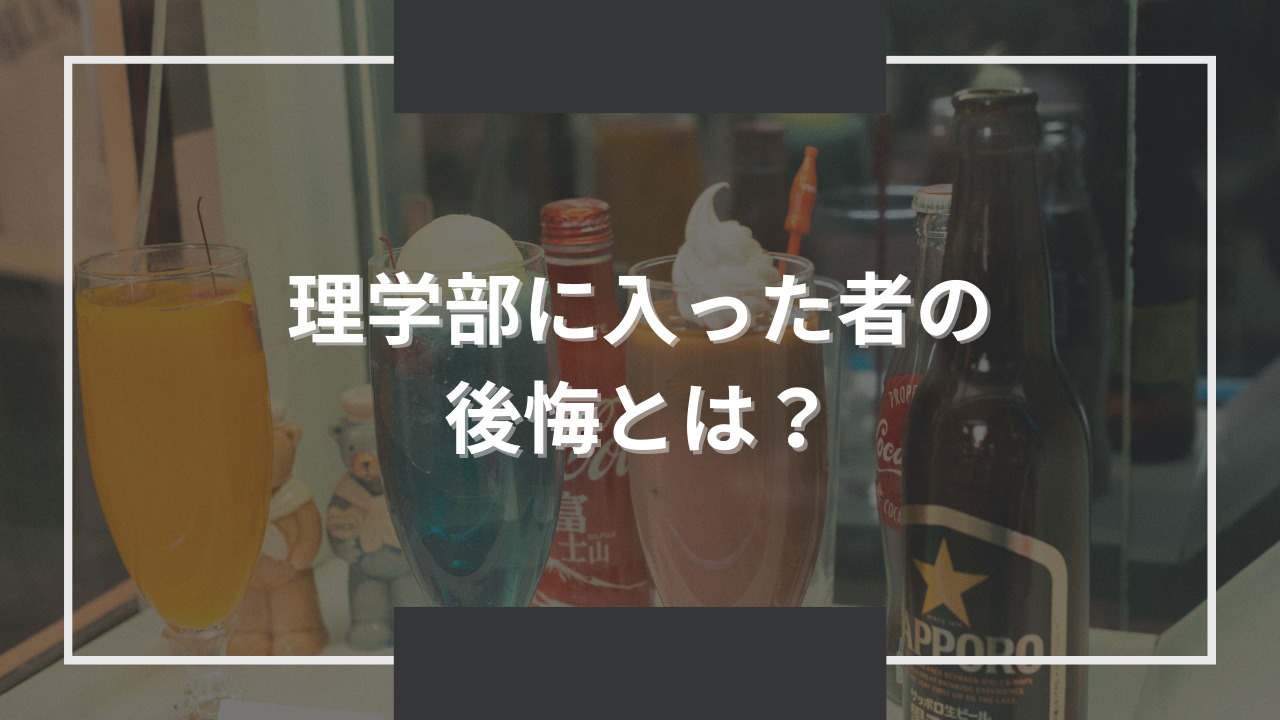
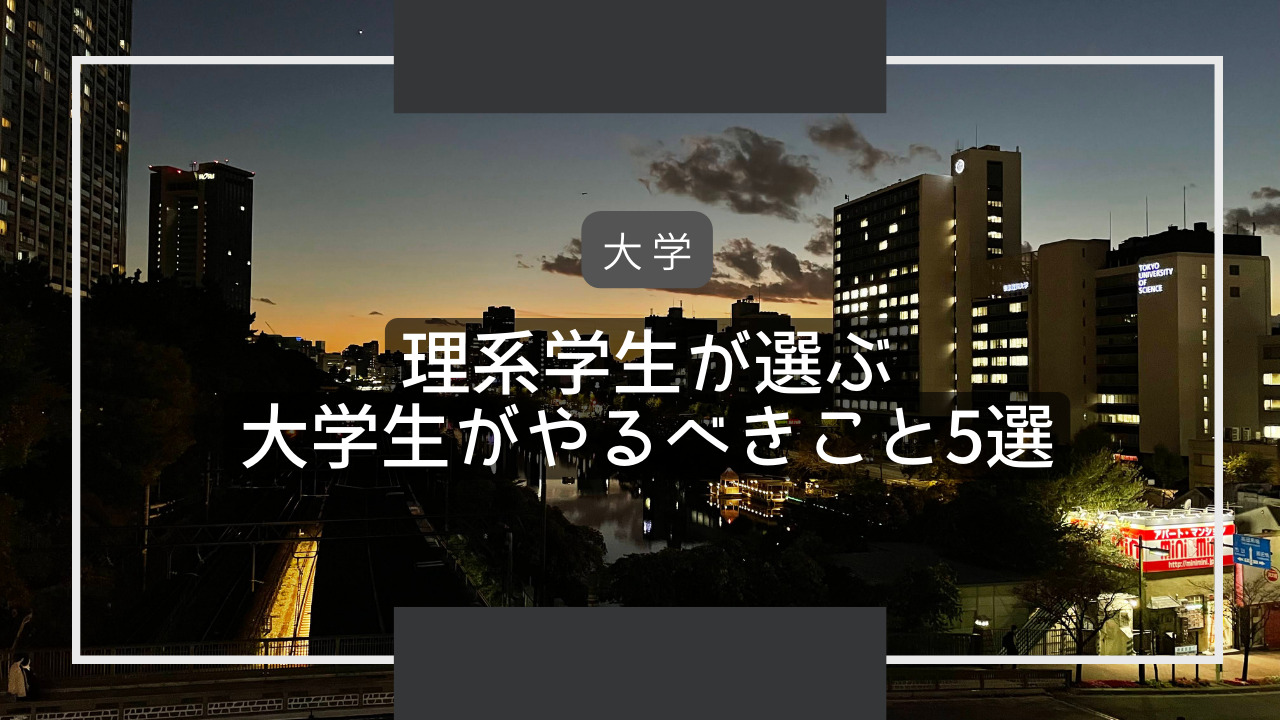

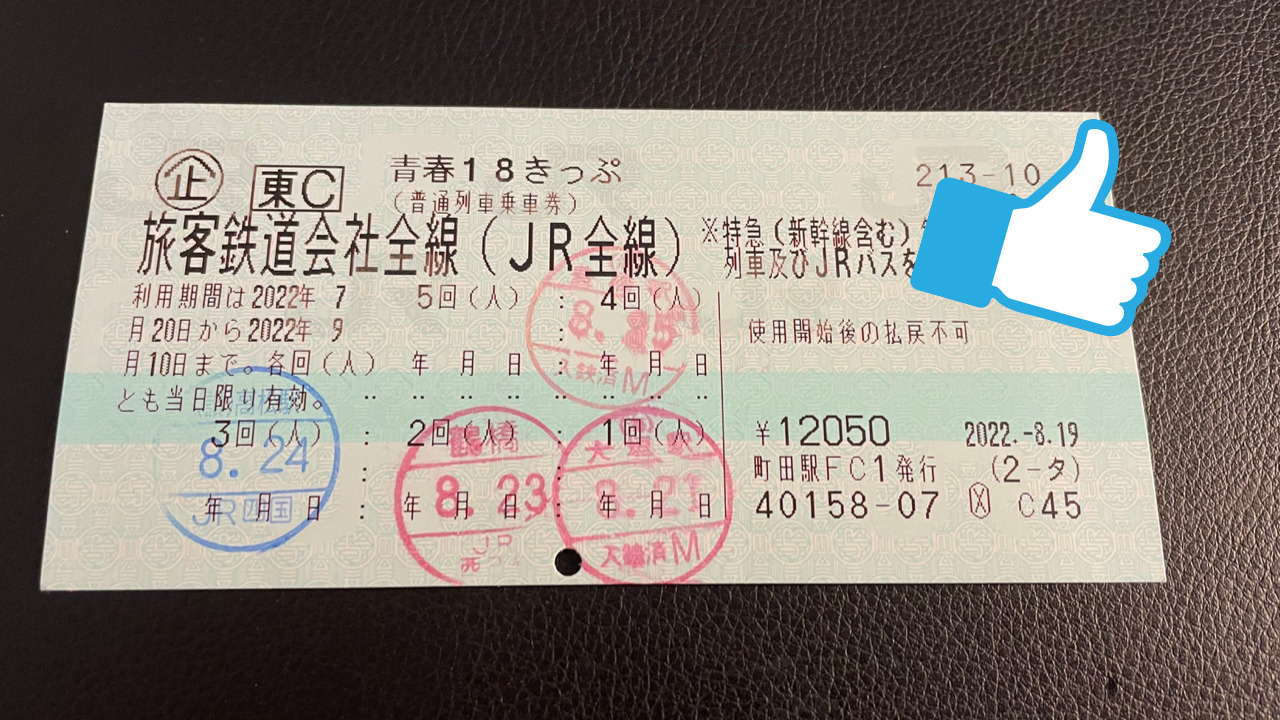


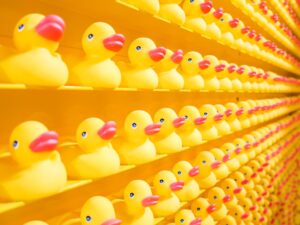

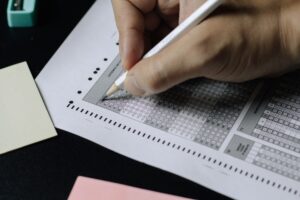


コメント